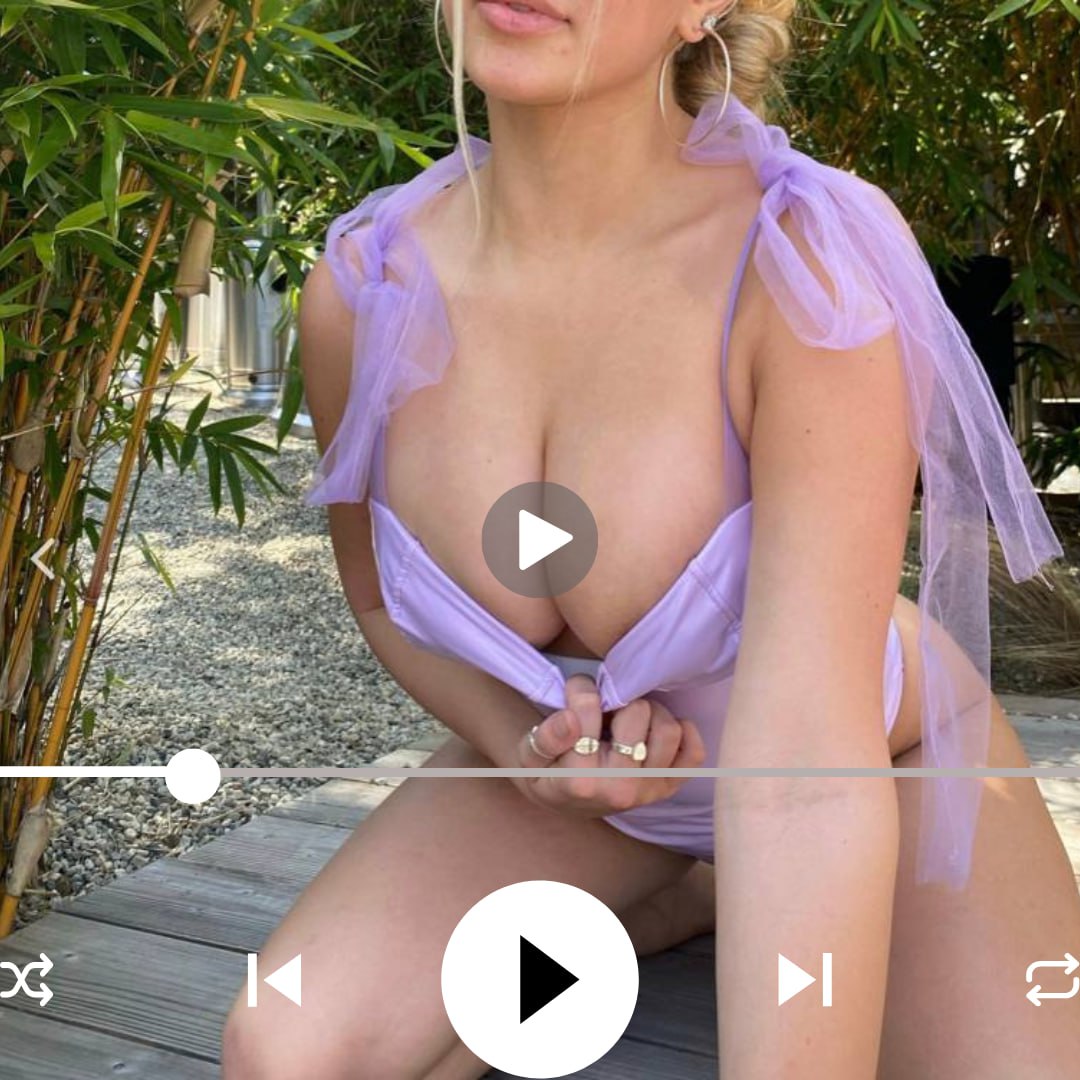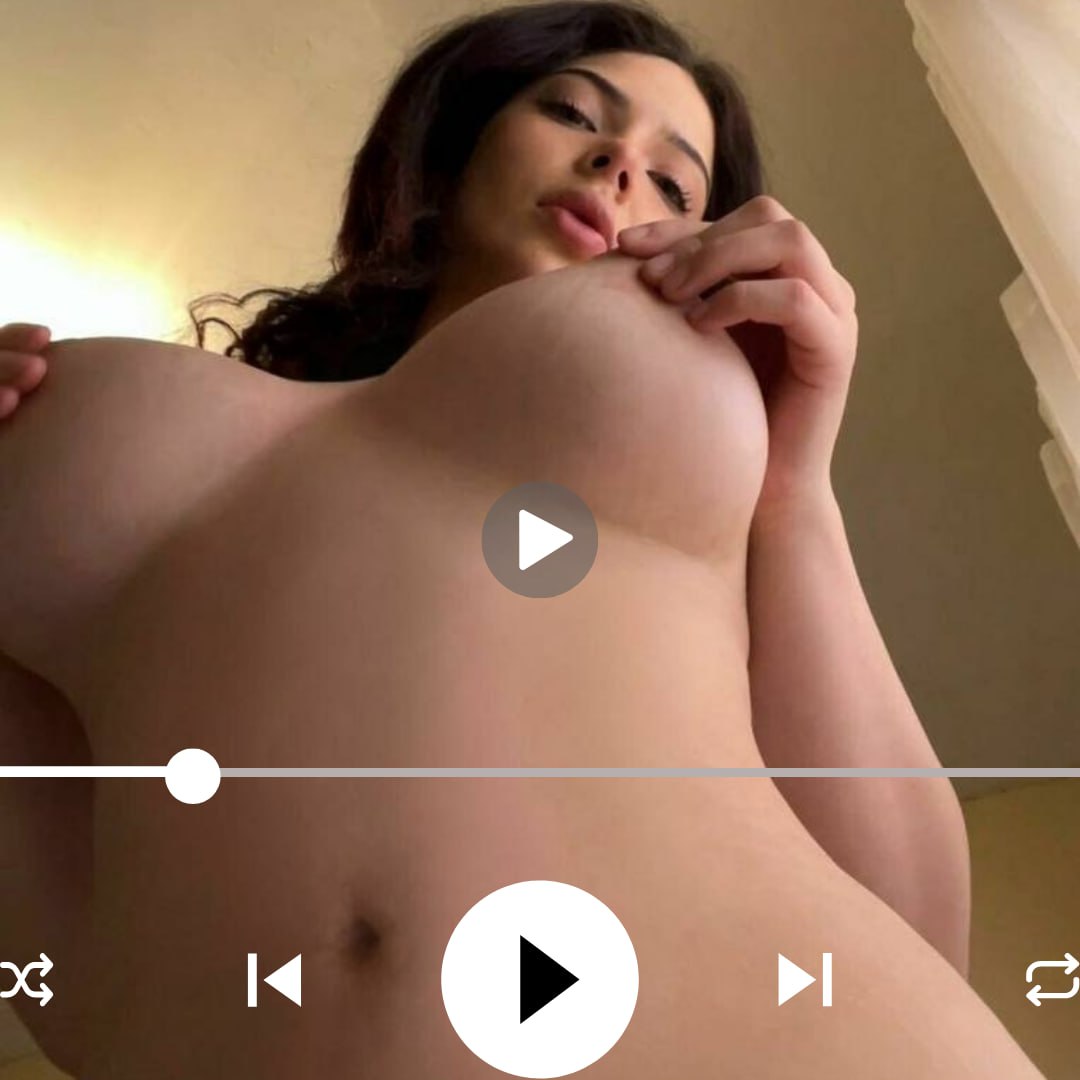公開日:2024/12/23 17:00 更新日:2024/12/23 17:00
この記事の画像を見る(3枚)
1975年の創刊第1号のときから「流されゆく日々」を執筆、49年目の今年12月2日に12000回を迎え、五木氏と寺田社長による記念対談を行った。たった1回の休みもなく書き続けてきた秘訣から、執筆スタイルまで「流されゆく日々」の舞台裏を語った。 ◇ ◇ ◇
寺田 12月2日に五木さんの「流されゆく日々」がついに12000回を迎えました。日刊現代の創刊が1975年で、創刊の第1号のときからこのコラムを書いていただいてますから49年です。改めてすごい年数、連載回数だなと驚いています。
五木 僕はつい今年の夏まで、戦後何十年にわたって病院に行ったことがなかったんですよ。ほとんどもう病院に行かずに戦後を過ごしてきたんですけど、その健康の秘訣に、いや全然健康じゃないんだけど毎日、日刊ゲンダイに書かなきゃいけないっていうのがあるんですね。寝込んだり入院したり、いろんなことがあっても、連載を休むわけにはいかない。最初の頃は、ちょっとストックもありましたが、20年くらいでスタイルが決まりました。毎日、1日3枚、ギリギリ深夜0時までに書く。それが生活のリズムになってきたんです。
寺田 創刊から20年経った頃ですね。それまでは取材旅行のために書きためたりも?
五木 往復書簡だとか、いろんなものを雑に載せてたんですけど、この何十年かは自分一人の日記のような形で書いてきたのです。
寺田 先生は病院に行ったことないとおっしゃいますが、もちろん体調が悪かったときもあるんですよね。実際、熱っぽかったりお腹が痛いとか。
五木 そういうことはしょっちゅうあります。もうこの年になると、さみだれ式にいろんなものが出てきますしね。だけど、僕はゲンダイのおかげで今日までやってこられたんじゃないかと思うんですよ。とにかく、書かなきゃいけないんだという気持ちの張りというか、そういうものがあったことで今日まで大過なくきたんじゃないかと。だって、盲腸だとか交通事故だとか、ありえますよね。でもそうなってくるとストックがないから、どうしても原稿が落ちます。そんなことは絶対にできない。偶然の事故でも避けなきゃいけない(笑)。病気も事故もケガも乗り越えて支えてくれる一番大きな杖になっているのがこの「流されゆく日々」なんです。僕は作家ではありますけれども、この仕事が自分のライフワークの一つだと思ってやってきた。
Page 2
公開日:2024/12/23 17:00 更新日:2024/12/23 17:00
 五木寛之氏(右)と日刊ゲンダイの寺田俊治社長(C)日刊ゲンダイ
五木寛之氏(右)と日刊ゲンダイの寺田俊治社長(C)日刊ゲンダイ
この記事の画像を見る(3枚)
寺田 ありがとうございます。連載の始まりは、前々社長の川鍋孝文さんの依頼でした。改めて1975年当時は五木さんにとってどういう時期だったかといいますと、1967年に「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞を取られて、69年には「青春の門・筑豊篇」の連載が始まり、76年には吉川英治賞、「戒厳令の夜」も出された。作家としては最も脂がのりきって一番忙しいときなんですね。そんなときに、創刊したからといって、川鍋さんはよく新聞連載を頼めたもんだなと、今考えると、大胆すぎるというか驚きます。
五木 川鍋さんとは個人的にもね、非常にいい友人だったんですよ。ですから、「ひとつお願いしますよ」というようなことでね。「すぐつぶれますから大丈夫ですよ」なんて言われて(笑)、それじゃあって始まったわけです。
寺田 五木さんは川鍋さんが亡くなったとき、追悼で「自由な風のような人だった」と書かれています。私たち後輩から見ると川鍋さんは一種の根無し草的なとこもあって、お二人が親しくなったのは作家と編集者という立場を超えたシンパシーというか、共通項のようなものがあったのかなと思いました。
五木 ありましたね。特に自由というものに関しての考え方が似ていたんです。ジャーナリストなんだけど根っこは文学青年で、酔っぱらうとランボーの詩をフランス語で朗読したり、いつまでも青年みたいな気分の抜けない人で、その辺が面白かったですね。川鍋さんのそういうキャラクターを日刊ゲンダイはずっと引き継いでいるんですよ。それが僕が日刊ゲンダイに愛着を持っている理由の一つなんです。川鍋という個性が脈々と現在の紙面に流れている。これがなくなったら、やっぱりここまで連載を頑張ってやるという気力はなかったと思いますね。
寺田 川鍋さんのDNAをひと言で言い表すのは難しいんですけど、まず1つはいい加減なんですね。
五木 たしかに(笑)。
寺田 それからアウトローなんですよ。でもイデオロギーうんぬんではないんです。川鍋さんがよく言ってたんですが、目線は低く。要するに上から見ちゃだめだと。ジャーナリズムとか、そういうこだわりを持たずに、もっと自由にと。それからしなやかに、というのも川鍋さんはよく言っていました。そういうことを思い出すにつれて、何か五木さんが連載で書かれていることとも、少し似ているところがあるのかなと思ったんですが。
五木 僕はやっぱり川鍋さんが残したものを自分は引き継いでいる、そんなふうに思っていますね。
寺田 え、五木さんが?
五木 ええ。僕は、彼が残したものをできるだけ大事にしてるんです。高いところから俯瞰して物を考えたり書いたりするのではなくて、草の間を這う虫のように、這いずり回って仕事をしていくという感覚とかね。ゲンダイの場合は、ちょっと(目線が)低すぎるって(笑)そしりもあるだろうけど。
寺田 うれしいですね。
Page 3
公開日:2024/12/23 17:00 更新日:2024/12/23 17:00
 日刊ゲンダイ創刊号に掲載された記念すべき第1回(1975年10月28日付)/(C)日刊ゲンダイ
日刊ゲンダイ創刊号に掲載された記念すべき第1回(1975年10月28日付)/(C)日刊ゲンダイ
この記事の画像を見る(3枚)
五木 自分で言うのもちょっとおこがましいんですけども、15年くらい前かな、世界の新聞史上で最も長い連載というのでギネスで表彰されたことがありました。いまはギネスと自分とどっちが長く続くかという感じでやってますけどね。この連載があることで、今日も一日やることがある、3枚足らずのコラムを書かなきゃいけないというのは、僕にとってフィジカルな意味での人生の支えでもあるんです。コラムを読んでいる読者がどこかにいるっていうのは、自分の後半生を支えていく上でものすごく大きかったというふうに自分では思いますね。ですから、心からこの連載、舞台を提供してくれたゲンダイに僕は感謝しているんです。
寺田 いえいえ、それはこちらこそです。私は時々思うんですけど、この「流されゆく日々」っていうのは、個々のコラムの中身はもちろんですが続いていること自体が表現じゃないかと。悠々と流れていること自体、その行為が1つの文芸作品、進行形の文学のように感じているんです。
五木 もう永遠に未完の連載かもしれないと思いますけどね(笑)。この「流されゆく日々」というタイトルは、昔、石川達三さんという作家がいらした。僕らは日本ペンクラブで、石川さんとは対立した革新派のグループだったんですが、非常に尊敬していました。その石川さんが純文学雑誌「新潮」に「流れゆく日々」というエッセーをずっと連載なさってたんです。僕は愛読していたんですけども、でも俺だったら違うなっていうね、流れゆく日々っていうのは岸辺に立って流れて行くいろんなものを、泰然と自分の視座を崩さずに眺めている。それ自体、すごく大事なことなんだけど、俺だったら一緒に上流から下流の方へ向かってゴミと一緒に流れていくぞと。そっち側にいたいという気持ちがあってね。それで「流れゆく日々」への敬意をひっくるめて、「流されゆく日々」というふうにタイトルをつけたんです。
寺田 一緒に流されていく。この連載のキーワードですね。
五木 それは、間違ってなかったと思います。いまだに基本はみんなが流れていくんだったら俺も一緒に流れるぞ、というね。そういう視座だけは外したくないと思って今日まで来たんですけど。いずれにしても正直なことを言って、時にはうんざりするときもありますよ。
寺田 アハハハ。
五木 今日クタクタになって帰ってきて、これから書かなきゃいけないのか、しかもアタマに書くことが浮かんでこないっていうようなときというのは、本当にもうね(笑)。時計を見るとどんどん時間が過ぎていくじゃありませんか。今、編集部で待っている人たちがいるんだなと思うと、本当に地獄です。短い原稿であるだけに、一歩ずつしか歩いていけない。集中して何百枚も書くのとは別の苦しみがあるのです。
寺田 五木さんでも書くことが思い浮かばなくて、どうしようと思うときがあるんですか。
五木 ありますね。原稿用紙を前にして、万年筆を持って白紙の原稿用紙を前にして頭抱えて2時間も3時間も唸っているときってありますよ。 (つづく)
▽五木寛之(いつき・ひろゆき) 1932年、福岡県生まれ。57年に早稲田大学を中退後、作詞家やルポライターなどを経て、66年「さらばモスクワ愚連隊」で小説現代新人賞、67年「蒼ざめた馬を見よ」で直木賞、76年「青春の門」で吉川英治文学賞を受賞。「親鸞」で毎日出版文化賞特別賞。近著に「五木寛之傑作対談集」(平凡社)がある。
▽寺田俊治(てらだ・しゅんじ) 1959年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部仏文科卒。1983年、日刊現代入社、編集局配属。編集局ニュース編集部局次長を経て2016年、代表取締役社長。

 五木寛之氏(C)日刊ゲンダイ
五木寛之氏(C)日刊ゲンダイ